源泉徴収票とは

源泉徴収票とは、会社が年末調整を行った後に作成する書類で会社が従業員に1年間いくら給料を支払って、いくら税金を徴収したかが記載されている書類のことです。
年末調整後に、源泉徴収簿をもとに源泉徴収票と給与支払報告書を作成します。
原則として、毎年1月には勤務先から従業員に交付されます。
受け取っていない場合には、すぐに会社に請求しましょう。
源泉徴収票が必要になる時
①年末調整後…年末調整後には、源泉徴収票を発行する義務があります。会社は従業員1人につき4枚作成し、従業員と税務署にそれぞれ1部ずつ市区町村に2部提出されます。
②従業員の退職時…従業員が退職した時には、会社は1月1日から退職時点までに支払った給与について源泉徴収票を発行する義務があります。
③従業員の収入証明が必要な時…従業員が自動車や住宅の購入の時にローンを組む時や、子どもを保育園に入れる時、高校無償化の適用を受ける時などは収入証明が必要になります。課税証明書の提出が求められることもありますが、源泉徴収票の提出が求められることもあります。
源泉徴収票の見方
所得税は会社から従業員に支払われた収入に対して直接税金が課税されるわけではありません。
給与収入から給与所得や所得控除を差し引いた額を給与所得といいます。
給与所得に決まった税率を掛けた額が所得税額となります。
支払い金額
支払金額の欄には、その年の1月から12月中に支払いの確定した給与等の総額が記載されます。
控除や源泉徴収される前の金額になります。一般的に、この金額を年収といいます。
給与所得控除の金額
給与所得控除後の金額欄には、支払金額から給与所得控除額を差し引いた金額が記載されます。
給与所得控除とは、給与収入額から一定の金額を差し引く仕組みのことになります。
給与収入1,625,000円までは55万円になります。

ここがポイント‼
《給与収入-給与所得控除額=給与所得金額》
サラリーマンは、個人事業主などのように必要経費が認められないため、サラリーマンの必要経費として給与所得控除という控除が設定されています。
現在、子育て世帯や介護世帯には税負担増が生じないように所得金額調整控除という制度が導入されています。
所得金額調整控除とは、扶養親族や障がい者がいる家庭の負担を減らすために税額を調整する制度になります。
所得控除額の合計額
所得控除の額の合計額欄は、給与所得控除後の金額から社会保険料控除・生命保険料控除・扶養家族控除・基礎控除などが差し引かれた額が記載されます。
所得控除とは、所得金額から差し引くことのできる金額のことで、15種類ほどあります。
基礎控除はすべての人が受けられる控除で、合計所得金額が2,400万円以下の場合に所得から48万円が控除されます。
※給与所得控除は、給与収入1,625,000円までは55万円になります。

ここがポイント‼
《給与収入103万-給与所得控除額55万ー基礎控除48万=給与所得金額0円(所得課税額0円)これが103万円の壁の仕組みになります。理解しておくと便利です。》
所得控除一覧
①雑損控除…災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される控除。

②医療費控除…一定額以上の医療費を支払った場合に適用される控除。

③社会保険控除…健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などを支払った場合に適用される控除。

④小規模企業共済等掛金控除…小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される控除。iDeCo

⑤生命保険料控除…生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される控除。

➅地震保険料控除…地震保険料を支払った場合に適用される控除。

⑦寄付金控除…ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用される控除。

⑧障害者控除…納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される控除。

⑨寡婦控除…配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される控除。

⑩ひとり親控除…納税者がひとり親であるときに適用される控除。

⑪勤労学生控除…学校に行きながら働いている場合に適用される控除。

⑫配偶者控除…配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される控除。

⑬配偶者特別控除…納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用される控除。

⑭扶養控除…16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される控除。

⑮基礎控除…すべての人に適用される控除。(所得合計が2,4000万円以下の場合)

源泉徴収税額
源泉徴収税額欄には、源泉所得税及び復興特別所得税の合計額が記載されています。
年末調整後の税額、つまり還付を受けた場合にはその額も合計した税額が表示されています。
年末調整していない場合には源泉徴収されていた金額の合計額が記載されることになります。
控除対象配偶者・配偶者特別控除の額
給与所得者と生計を一にする配偶者がいる場合には、要件に該当した配偶者の所得に応じて所得控除を受けることができます。
控除額は、納税者本人の合計所得金額によって異なります。
控除対象扶養親族・障害者
扶養控除とは、所得が一定金額以下の満16歳以上の親族等がいる場合に受けられる控除です。
控除額は扶養親族の年齢によって変わります。
社会保険料等の金額
給料から天引きされる健康保険・介護保険・厚生年金保険などの社会保険料の合計額が記載されます。
この3つを合計すると給与の約15%になります。
生命保険料・地震保険料・住宅借入金等特別控除
生命保険料や地震保険料を支払った時には、一定の所得控除を受けることができます。
生命保険料の控除額は、旧契約は上限5万円・新契約は上限4万円です。
地震保険料の控除額は、上限は5万円です。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得または増改築等の場合で、一定の要件に該当した場合に所得から控除されるものです。
控除を受ける1年目は、本人が確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整の対象となります。
まとめ
源泉徴収票を読むことができると、年末調整が正しく計算されているか、確認することができます。
上手に控除を申告し節税することはサラリーマンにとっての権利です。上手に活用しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
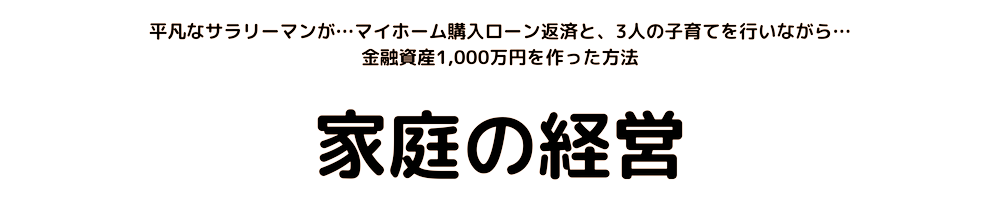
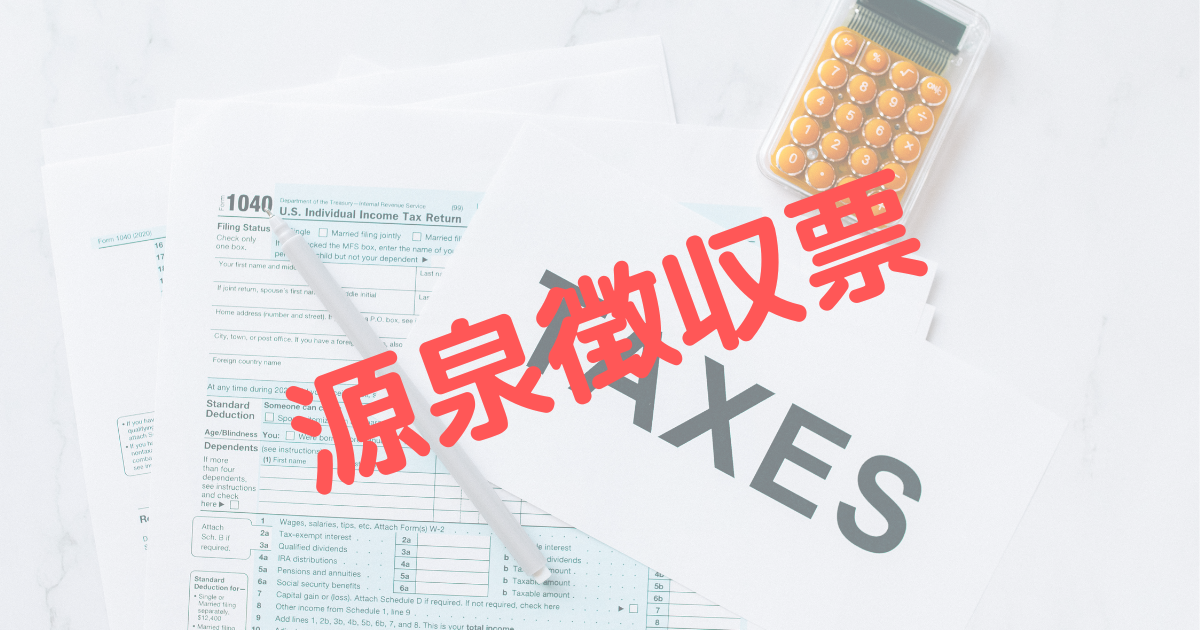
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント