小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除とは、対象となる共済制度の掛金を支払った場合、その全額を所得から控除できるものです。
小規模企業共済等掛金控除の対象
①小規模企業共済制度の掛金
②個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金
③企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
④心身障害者扶養共済制度の掛金
控除額の計算方法
小規模企業共済等掛金控除は、1年間に支払った掛金の全額が所得から控除できます。
基本的に、控除額に上限はありません。
小規模企業共済50万円とiDeCoの年間掛金が27.6万円なら、控除額は77.6万円になります。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模事業の経営者のための退職金制度です。
個人事業主や企業経営者には、会社等に勤めている方と違って退職金がありません。
個人事業主や小規模企業の経営者や役員が廃業や退職時の生活資金などを作れるようにと、小規模企業共済という制度が作られました。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入資格があるのは、基本的に個人事業主・フリーランス・小規模会社の経営者や役員となります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金の上乗せを目的とした私的年金制度です
個人が掛金を拠出し自分で運用して、老後に元金と運用益を受け取る仕組みになっています。
iDeCoの掛金として拠出した分は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり課税対象となる所得から控除できます。
毎月23,000円の掛金を拠出した場合は、276,000円の所得控除を利用できるになります。
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは、企業が掛金を毎月拠出し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。
従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定などをし運用を行います。
定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)もしくは年金の形式で受け取ります。
積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。
心身障害者扶養共済制度とは
心身障害者扶養救済制度とは、障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなったときなどに障害のある方に対し一定額の年金を一生涯支給する制度です。
心身障害者扶養救済制度の掛金として拠出した分は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、課税対象となる所得から控除できます。
保護者の加入要件
①障害のある方を現に扶養している保護者(親族)
②その都道府県・指定都市内に住所があること
③加入時の年度の4月1日時点での年齢が65歳未満であること
④特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
⑤障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のある方の加入要件
①将来独立自活することが困難であること
②知的障害
③身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級に該当する
④精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記②③と同程度と認められる
iDeCoと小規模企業共済との併用
iDeCoと小規模企業共済は併用できます。(小規模企業の経営者・役員・個人事業主のみ)
iDeCoも小規模企業共済も小規模企業共済等掛金控除の対象です。
両方の掛金を所得控除として適用すると、最大1,656,000円の控除が受けられます。
しかしながら、それぞれの掛金を毎月支払っていくのはなかなか難しい部分もあります。
個人事業主の場合は小規模企業共済を優先する方がおすすめです。
まとめ
給与所得のサラリーマンでしたら、企業型DC(企業型確定拠出年金)とiDeCo(個人型確定拠出年金)が控除適用対象になるかと思います。
我が家の場合は、夫婦でiDeCoに加入しております。

満額加入なので、年額552,000円の所得控除を受けております。
所得税率にもよりますが、課税10%で55,200円・5%で27,600円の所得税の節税になります。
企業型DCのない企業に勤務しているため、小規模企業共済等掛金控除はiDeCoのみになります。

ここがポイント‼
《2022年10月より、iDeCoの加入条件が緩和されました。
誰でも加入できるようになったので全額所得控除で節税しながら自分年金を作ってください。》
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
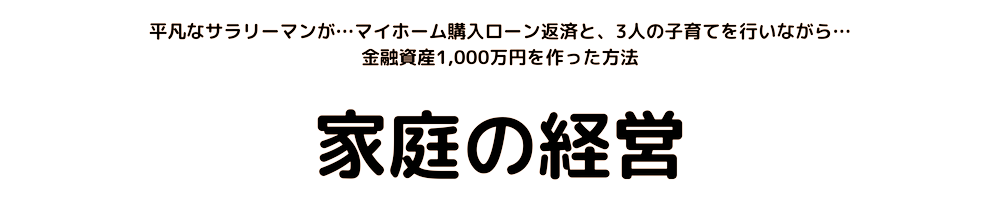

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント