生命保険控除とは
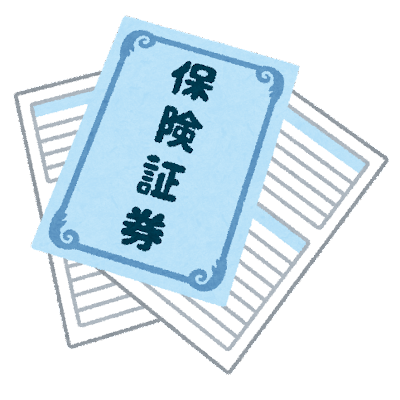
生命保険控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った保険料に応じて控除額が決まります。
平成24年の法改正により、保険をいつ契約したかによって控除できる対象や上限額が変わってきます。
平成23年12月末までに契約した保険は旧制度、平成24年1月以降に契約した保険は新制度となります。
一般生命保険料
生存または死亡した場合などに一定額の保険金が支払われる保険が対象になります。
保険金の受取人が、保険料を支払う本人またはその配偶者・その他の親族である必要があります。
定期保険・終身保険・養老保険・学資保険などが該当します。
介護医療保険料(新制度のみ)
疾病または身体の傷害などにより保険金・給付金が支払われる保険が対象になります。
医療保険・がん保険・介護保険・就業不能保険などが該当します。
個人年金保険料
条件を満たしている個人年金保険の契約が対象になります。
①年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者
②保険料を10年以上にわたって定期的に支払う
③60歳になってから、10年以上の定期もしくは終身で年金を受けとる
④個人年金保険料税制適格特約を付加している
⑤年金の受取人が被保険者と同一
新制度とは
新制度となる生命保険料控除では、介護医療保険料が控除対象に加わり、3つの保険料の定義を保障の内容によって分類されています。
旧制度と新制度を比べると、保険料を控除できる上限額が引き下げられています。
新制度からは、8万円以上の保険料を支払う人は一律4万円までしか控除されません。
保険料を10万円以上払っていても8万円を払っていても、4万円しか控除されないことになります。
保険期間が5年未満の生命保険など、生命保険料控除の対象にならないものもあるので確認が必要です。
自分の入っている保険が控除の対象となるか?どの保険料控除に分類されるか?については、
毎年10月ごろに保険会社から送られてくる保険料控除の証明書に記載されています。
保険料控除の証明書は、年末調整や確定申告の際に必要になるので、大切に保管しておきましょう。
2019年より電子的控除証明書によって控除証明書を交付することも可能になりました。(電子データ)
生命保険料控除の限度額
一般生命保険料…旧制度50,000円→新制度40,000円
個人年金保険料…旧制度50,000円→新制度40,000円
介護医療保険料…旧制度-設定なし→新制度40,000円
旧制度50,000円×2=100,000円→新制度40,000円×3=120,000円
生命保険料控除の計算方法
年間払込保険料額20,000円以下→払込保険料全額
年間払込保険料額20,000円~40,000円→(払込保険料×1/2)+10,000円
年間払込保険料額40,000円~80,000円→(払込保険料×1/4)+20,000円
年間払込保険料額80,000円超→一律40,000円
地震保険料控除とは

地震保険控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った保険料に応じて控除額が決まります。
地震保険とは損害保険の一部で単体では加入できず、火災保険とセットでなければ加入できません。
基本的に保険料全額が控除対象となる。ただし上限は所得税が最高5万円になります。
複数年分の地震保険料をまとめて支払っても、毎年控除を受けることができます。
火災保険料は控除対象外になります。
損害保険料控除が廃止された経過措置として、一定の要件を満たした長期損害保険については地震保険料控除の対象にできます。
一定の要件とは、平成18年12月31日以前に契約した、契約期間が10年以上の損害保険契約。
これが、旧長期損害保険となります。
旧長期損害保険料の控除額の上限は1万5,000円。
地震保険と長期損害保険の両方を契約している場合は、合算額の上限が5万円になります。
つまり、地震保険料が5万円以上であれば、旧長期損害保険へ適用できないことになります。
地震保険料控除額と上限額
地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計が地震保険料控除額(上限50,000円)
地震保険料控除の計算方法
地震保険料・年間払込保険料額50,000円以下…払込保険料全額
地震保険料・年間払込保険料額50,000円超…50,000円
旧長期損害保険料控除の計算方法
旧長期損害保険料・年間払込保険料額10,000円以下…払込保険料全額
旧長期損害保険料・年間払込保険料額10,000円~20,000円…(払込保険料×1/2)+5,000円
旧長期損害保険料・年間払込保険料額20,000円超…15,000円
まとめ
生命保険料控除の上限12万円と地震保険の上限5万円で合わせて17万円になります。
『生命保険は節税になります。』と言われたことがあるかと思います。
月1万円の生命保険料→所得税率10%で1,000円の節税、所得税率5%で500円の節税です。
月2万円の生命保険料→所得税率10%で1,000円の節税、所得税率5%で500円の節税です。
月2万円のiDeCo→所得税率10%で2000円の節税、所得税率5%で1000円の節税です。

どう考えても、iDeCoの方が節税になると思います。
我が家の場合は、生命保険は県民共済で月2,000円の掛金で保障を得ています。

個人年金保険はiDeCoで月23,000円×夫婦2人=月46,000円→所得税率10%で4,600円の節税。
地震保険は加入していません。年間払込保険料にしては災害時の保障が小さすぎるという考えです。

ここがポイント‼
《節税になるからと言われて…生命保険に加入するのは、いかがかなぁ~と思います。
それなら、全額所得控除のiDeCoの加入拠出をおすすめします。》
みなさんの状況に応じて、目的を明確にしてご検討ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
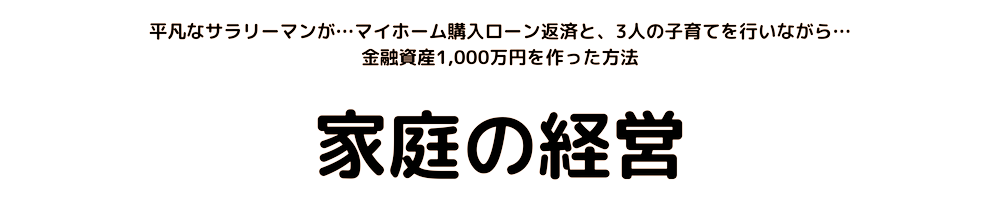

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント