リスク細分型自動車保険

自動車保険は、保険料算出のためにリスクとなる要因を膨大な過去データを細かく分析して算出された基本料率を用いて保険料を決めています。
リスク細分型自動車保険では、保険会社ごとに異なる基本料率を基にノンフリート等級別割引などの各種割引、補償を拡充する特約保険料を加算して個々の契約者に合わせた保険料を算出します。
異なるリスク細分は、保険業法施行規則の第12条と言う法律に定められた、9つの要因を基に保険料が算出されています。
年齢
従来以上に細分化され、20歳以下・21~25歳・26歳~34歳・35歳以上など、主たる運転者(被保険者)を年齢ごとにリスクを算定して保険料を算出しています。
昨今は高齢者の事故が増加しており今後の高齢者人口増加を踏まえて、高齢者を不担保とする割引などが考慮されています。
性別
男女差による保険料は性別差別などの問題を持っているため、現在の保険商品では保険料への直接反映はごくわずかになっています。
主に運転をする記名被保険者また契約者や指定運転者の男女差を保険料に反映することもあります。
運転歴
現在、ノンフリート等級制度による割引割増が契約歴や事故歴によって大きく反映されています。
運転免許証の色がゴールドの場合、割引を設けている保険会社もあります。
営業用・自家用その他自動車の使用目的
運行の目的によってリスクは大きく変わりますので、次のように使用目的別のリスク細分を行う保険会社が増えています。
①日常・レジャーのみ(リスク小)・②通勤・通学の利用あり(リスク中)・③業務使用(リスク大)の3つの区分ごとに異なる保険料率が設定されています。
年間走行距離その他自動車の使用状況
1年間に走る距離もリスクの細分化に反映させている自動車保険があります。
走行距離のリスク区分は保険会社によって違い、いくつかのパターンが有ります。
走行距離区分に対しての見解は難しく、採用を見送っている保険会社もあります。
地域
本土・諸島部・沖縄などの区分は、自賠責保険を始め以前の自動車保険でも保険料に差がありました。
リスク細分化をさらに進め、北海道/東北/関東・甲信越/東海・北陸/近畿・中国/四国/九州・沖縄といった地域区分を採用する保険会社もあります。
自動車の種別
自動車の車種や種別ごとに毎年の自動車事故による損害の内容を検討し、車種種別ごとに料率が算定されています。
以前は車両保険部分だけでしたが、現在は賠償クラス・搭乗者傷害クラスなどの区分がされるようになり保険料の細分化が進んでいます。
自動車の安全装置の有無
以前よりエアバッグ付、ABSなどのすべり止め防止装置付などの割引がありました。
現在は、車種ごとの賠償クラス、搭乗者傷害クラスと併用した形でリスク細分が行われています。
自動車の所有台数
所有台数によるリスク細分は、ノンフリート多数割引・複数所有などの割引で反映されています。
ノンフリート等級制度
フリートとは、10台以上まとめての自動車保険契約のことです。
これはノンフリートですから、フリートではないことを意味しています。
個人の自動車保険契約の割引率・割増率を決める基準のことをノンフリート等級制度と言います。
総合自動車保険
対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害保険・搭乗者傷害保険・車両保険・その他の補償がセットになった保険商品のことになります。
対人賠償責任保険
契約の車の自動車事故により、他人を死傷させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金を受けることができます。
対物賠償責任保険
契約の車の自動車事故により、他人の財物に損害を与えることで被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金を受けることができます。
人身傷害保険
補償の対象となる事故により被保険者が死傷した場合に、損害(治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費など)に対して保険金を受けることができます。
搭乗者傷害保険
被保険者が契約の車の自動車事故により、死傷した場合に保険金を受けることができます。
車両保険
衝突や接触などの偶然な事故により契約の車に損害が生じた場合に、保険金を受けることができます。
その他の補償
弁護士費用特約・人身傷害特約・車両搬送費用特約などのオプション契約になります。
まとめ
自動車保険を必要最小限で契約するのは、かなり難しいと思います。
必要最小限の契約で最大限の補償を受けるのは、かなりの至難の業です。
どれが必要でどれが不必要であるかは、前提条件をそろえないと判明しませんし正解もありません。

ここがポイント‼
《リスク細分型・総合自動車保険の仕組みを理解し、必要最小限の保険契約をしましょう!》

保険契約は充実させれば安心ですが、その分コストが継続的にかかります。

保険契約の最適化を考えていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
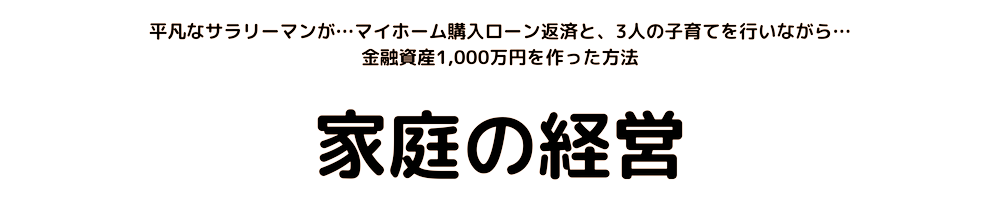

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント