年末調整とは

給与支払者は、毎月の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっています。
その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額と一致しないのが普通です。
この一致しない理由は、
①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正し
く計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を年末調整と呼んでいます。

ここがポイント‼
年末調整は、必ず還付されるものではありません。
徴収されることもありますので、お気をつけください。
一般に給与所得者は、ひとつの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。
このような人が、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうと、確定申告などの手続を行う必要がなくなります。
年末調整は、大事な手続きになります。
対象となる人
①1年を通じて勤務している人
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③死亡により退職した人
④著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職ができないと見込れる人
⑤12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
➅パートタイマーなどの人が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人
⑦年の途中で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により非居住者となった人
提出申告書
①扶養控除等申告書
②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
③保険料控除申告書
④住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除対象者のみ)
扶養控除等申告書
扶養控除とは、扶養控除対象となる親族がいる場合に一定額の控除が受けられる制度のことです。
扶養控除申告書を提出することで、年末調整で控除を受けられるようになります。
扶養控除申告書を提出しなかった場合、年末調整で扶養控除を受けることができません。
年末調整に扶養控除が反映されないと、自分で確定申告を行う必要があります。
記入項目
①勤務先・納税者の本人情報
所轄税務署長等には、勤務先企業本社の住所がある税務署名を記入してください。
市区町村長には、納税者自身の住所がある市区町村を記入しましょう。
あとは、本人情報を記入します。

独身・単身の人、扶養家族等がいない人はここまでの記入で終了となります。
②源泉控除対象配偶者(A)
次の条件に当てはまる場合は、源泉控除対象配偶者として記載が必要です。
①納税者の所得が900万円(年収1,120万円)以下
②配偶者の所得の見積金額が85万円(年収150万円)以下
③配偶者が青色申告の事業者として給与を受け取っていないことと白色申告書の事業専従者でないこと

所得とは、収入から必要経費を差し引いた後の金額のことです。
③控除対象扶養親族(B)
控除対象扶養親族とは次の条件に当てはまる人になります。
①配偶者以外
②給与所得者と生計を共にしている
③合計所得金額の見積額が48万円(給与収入103万円)以下
④青色事業専従者として給与が支払われていないことと白色事業専従者でないこと
④障害者、寡婦・寡夫、勤労学生(C)
扶養家族または本人が以下のいずれかに該当する場合は記入します。
①障害者…本人または生計を一つにする配偶者や親族に障害があるときに控除の申請ができます。
②寡婦・寡夫…配偶者と死別・離婚をしたあと再婚しておらず、子どもがいる人が対象になります。
③勤労学生…本人が学生の場合に受けることができる控除になります。証明書(学生証)が必要。

勤労による所得(給与所得など)があること
合計所得が65万円以下、勤労以外の所得が10万円以下であること
高等学校や専修学校、認定職業訓練学校、もしくは大学などの学生であること
⑤他の所得者が控除を受ける扶養親族等(D)
申告書提出者以外が、家族を扶養親族として申請するときに記載します。
⑥16歳未満の扶養親族
16歳未満の子供がいる場合、記載します。
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
基礎控除とは、本人の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
配偶者控除とは、本人と生計を一つにしている年間の合計所得額が48万円以下の配偶者がおり、かつ本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられる控除になります。(最大38万円)
配偶者特別控除とは、申告者と生計を一つにしている年間の合計所得額が48万円超133万円以下の配偶者がおり、かつ本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられる控除です。(最大38万円)
所得金額調整控除とは、給与の収入金額が850万円を超える給与所得者が、①23歳未満の扶養親族を有する②申告者ご本人が特別障害者③申告者の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者に該当すると受けられる控除になります。(最大15万円)
基礎控除
合計所得金額が2,400万円以下の場合48万円
2,400万円超2,450万円以下の場合32万円
2,450万円超2,500万円以下の場合16万円
基礎控除申告書を記入する前に、給与所得の収入金額と給与所得以外の所得の合計額を調べておく必要があります。
配偶者控除
①配偶者氏名、個人番号、生年月日を記入します。
②配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を記入します。
③控除額計算欄を使用して算出し記入します。
所得金額調整控除
給与収入金額が850万円以下の場合は、記載する必要はありません。
①該当する要件にチェックを入れます。
②要件欄であなた自身が障害者以外にチェックを入れた場合、扶養親族等の氏名、個人番号、生年月日、続柄、所得金額、住所または居所を記入します。
③特別障害者欄にチェックした場合は、最右枠内に特別障害者に該当する事実を記入しましょう。
保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模共済等掛金控除を受けるために提出する書類です。
加入している保険会社等から送られてくる保険料控除証明書の中に、記入事項が記載されておりますので、そのまま写す感じになります。
生命保険料控除
生命保険料控除欄では、一般の生命保険料(新契約・旧契約)、介護保険料、個人年金保険料(新契約・旧契約)から控除額を算出します。
保険料控除証明書や契約証を見ながら記入するイメージです。
記入項目は、保険会社等の名称・保険の種類・保険期間・契約者名・受取人・受取人の続柄・新旧区分・本年中に支払った保険料です。
証明書の内容を正確に転記する必要があるため、記入箇所を間違えないように気をつけましょう。
新保険料等の合計金額を計算式Ⅰに、旧保険料等の合計金額を計算式Ⅱにあてはめます。
一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険それぞれの控除額が計算できたら、すべての控除額を合計し生命保険料控除額を算出しましょう。
記入の際に使用した保険料控除証明書は申告書に添付する必要があります。
紛失しないように、気をつけましょう。
地震保険料控除
地震保険料欄では、地震保険料から地震保険料控除額を算出します。
証明書をもとに、保険会社等の名称・保険の種類・保険期間・契約者名・契約者の続柄・地震旧長期区分・本年中に支払った保険料を記入します。
記入した保険料を、地震保険料と旧長期障害保険料それぞれで合計し、Ⓐに記入します。最後に、Ⓑ©で求めた合計額を計算式にあてはめ、地震保険料控除額を計算してください。
地震保険料控除を適用する場合は、保険等の対象となった家屋等に居住または家財を利用している人が、本人または生計を一にする親族でなければなりません。
記入の際に使用した地震保険料控除証明書は申告書に添付する必要があります。
紛失しないように、気をつけましょう。
社会保険料控除
国民年金保険料等、本人が直接支払った社会保険料がある場合、年末調整することで社会保険料の合計が所得から控除されます。
給与から差し引かれた社会保険料は年末調整の対象外なので、注意してください。
社会保険料控除欄には、社会保険の種類・保険料支払先の名称・保険料の負担者・保険料負担者の続柄・本年中に支払った保険料を記入します。
社会保険料控除欄では、支払った保険料を合計し記入しましょう。
国民年金の保険料や、国民年金基金の加入者として負担する掛金を記載する場合、その証明書の添付が必要になります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除欄では、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など、自身が直接支払った小規模企業共済等掛金を記載します。
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
③確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金(iDeCo)
④心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金
それぞれの掛金を掛金の証明書等の合計額を記入します。
記入の際に使用した証明書は申告書に添付する必要があります。
紛失しないように、気をつけましょう。
住宅借入金特別控除申告書
個人が住宅ローンを利用して自宅を取得した場合、住宅借入金の年末残高に応じて一定額を税額から直接控除できます。
給与所得者の場合、初年分は確定申告による適用を受ける必要があります。
2年目以降は年末調整の際に控除の適用を受けられます。
本人の合計所得金額が3,000万円を超えると控除を受けられません。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を参考に各項目を記入します。
申告書内の管轄税務署名・給与の支払者名称・給与の支払者の所在地・申告者氏名・申告者の住所または居所を記入します。
証明書をもとに、新築、購入および増改築に係る住宅借入金等の年末残高や特定増改築等の費用の額等を①~⑤に記入します。
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合は、➅⑦にも記入が必要です。
①~⑤に記載した金額をもとに、⑧を記入します。
住宅借入金等の年末残高に控除率をかけ、算出した金額と控除の限度額を比べ、どちらか低い金額を記入してください。
控除率や控除限度額は居住を開始した時期によって異なります。
2022年1月1日以降に住宅の居住を開始した場合は、控除率が0.7%となるため注意してください。
まとめ
年末調整は、国民の義務である納税に関する大事な手続きです。

ここがポイント‼
《毎年変わる制度改正点を把握して、記入漏れ・申告漏れがないか確認して提出しましょう。》
年末調整に関係する書類は、必ず提出期限内に提出してください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
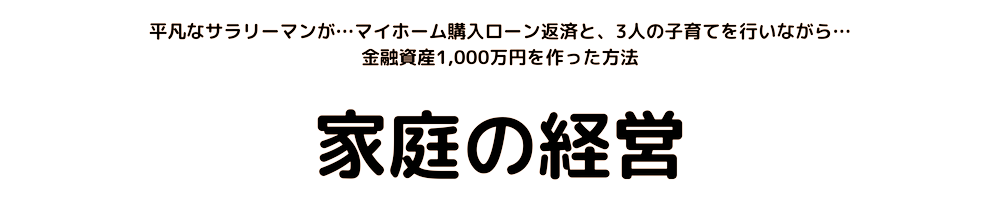

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント