産前産後休業制度とは
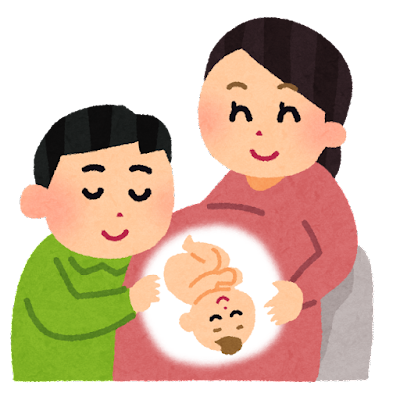
産前産後休業制度とは、出産の時期に認められた休暇のことで労働基準法で定められています。
出産前の準備期間に取得する産前休業と、産後の体を回復させるために取得する産後休業のことを合わせて産休と呼びます。
労働基準法で定められた、出産するすべての人が取得できる制度です。
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取得できると決まっています。
また双子など多胎妊娠の場合は予定日の14週間前から産休を取得できます。
育休休業制度とは
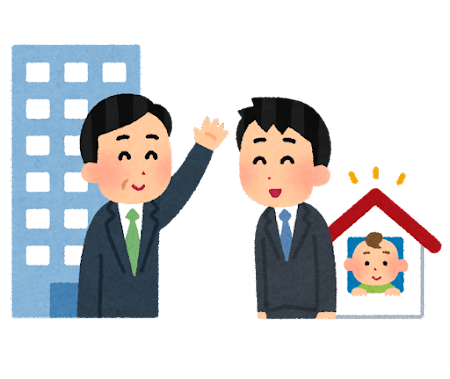
育児休業制度とは、原則として1歳に満たない子どもを養育する労働者が会社に申し出ることで、養育する期間を休業できる制度です。
子どもが1歳を超えても保育所に入れないなどの理由があれば、最長で2歳になるまで延長も可能です。
育児休業取得条件は、①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること②子が1歳6カ月に達する日までに労働契約の期間が満了することがないことになります。
産前産後休業は雇用形態にかかわらずだれでも取得できますが、育児休業は取得できるケースとできないケースがあります。
産前産後休業とは違い、女性だけでなく男性も取ることができます。
給付金制度
産休育休中にも受け取れる給付金などをご紹介したいと思います。
出産育児一時金
出産時の経済的な負担を軽減する目的で、出産育児一時金が支給されています。
通常は子どもひとりにつき42万円が支給されます。
2023年度から出産育児一時金42万円が47万円へ増額されます。
出産育児一時金には直接支払い制度もあります。
健康保険組合から出産で利用した医療機関に直接支払いをしてもらう制度になります。
医療機関での出産費用が出産育児一時金の金額よりも少なかった場合には、差額が申請者本人に支給されます。

申請の期限は出産から2年以内です。
期限内に申請しないと受け取れなくなりますので、忘れずに手続きしてください。
出産手当金
出産手当金は、産休中に給与が受け取れない場合に支給される手当です。
産休中の有給消化や、勤務先の規定で産休中にも給与が支給されている場合などは受け取れません。
出産までに1年以上継続して健康保険加入していれば、雇用形態に関わらず契約社員や派遣社員でも受け取れます。
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間を対象として支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
支給額は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

ここがポイント‼
《会社の健康保険・公務員の共済組合の被保険者本人が対象になります。》
育児休業給付金
育児休業給付金は、休業開始時点での給与の日額の67%の金額を育休中に受け取れる制度になります。
無期雇用の場合は、休業開始までの2年間に12か月間雇用保険に加入している方が対象です。
有期雇用契約の場合は同じ勤務先で1年以上勤めて、雇用保険に加入している方が対象です。

育児休業給付金は、育児休業後に職場復帰することを前提に支給されるものですので、
育休後に退職の予定がある方は対象外になります。
子ども政策の司令塔となる『こども家庭庁』
子ども政策の司令塔となる、こども家庭庁が2023年4月に設置されることが決まっています。
こども家庭庁の中は、企画立案・総合調整部門、成育部門、支援部門という3つの部門が置かれます。
企画立案・総合調整部門
企画立案・総合調整部門は、全体をとりまとめる部門になります。
これまで各府省庁が別々に行ってきた子ども政策を一元的に集約し、子どもや若者から意見を聴くなどして、子ども政策に関連する大綱を作成するほか、デジタル庁などとも連携して個々の子どもや家庭の状況や支援の内容などの情報を集約するデータベースを整備することになっている。
成育部門
成育部門は、子どもの安心安全な成長のための政策立案を行う部門になります。
文部科学省と協議して、幼稚園や保育所・認定こども園の教育や保育の内容の基準を策定したり、子どもと関わる仕事をする人の犯罪歴をチェックするなど子供たちの安心安全な環境を構築することになっています。
支援部門
支援部門は、虐待やいじめ、ひとり親家庭など困難を抱える子どもや家庭の支援にあたる部門になります。
重大ないじめがあった場合には、文部科学省に説明や資料の提出を求める勧告などを行ったり、ヤングケアラーの早期把握に努め、福祉や介護・医療などの関係者が連携して必要な支援を行うことになっています。
障害児の支援や施設や里親のもとで育った若者などに対しての支援も行うことになっています。
まとめ
2022年以降、日本政府が子育て支援政策を充実させてきています。
現在の若い世代は、出産子育て・仕事・プライベートと忙しく過ごしていることと思います。
国の支援・制度を上手に活用して、人生を充実させていただきたいと思います。
できるだけ理解しやすく制度のお伝えし、子育て世代の応援をしていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
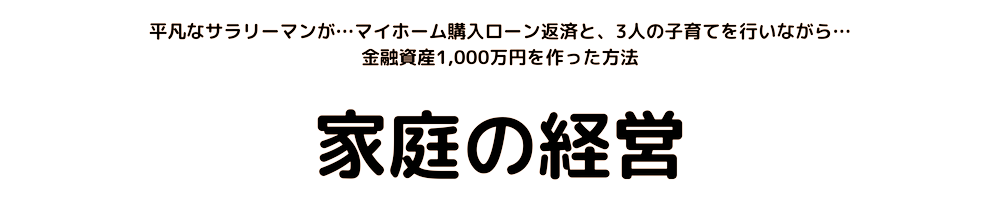

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント