基礎控除とは

基礎控除とは、すべての納税者を対象に無条件で差し引く所得控除のことになります。
サラリーマンであっても、個人事業主であっても、納税者(申告者)すべてに適用される制度です。
所得税計算をする際の基礎控除の額は48万円です。
2020年より、
基礎控除の金額が10万円引き上げられて48万円となり、給与所得控除が10万円減額されました。
基礎控除…38万円→48万円
給与所得控除…65万円→55万円
青色申告特別控除の額も10万円減額され、65万円から55万円になりました。
青色申告特別控除…65万円→55万円
住民税の基礎控除
基礎控除には、所得税の計算をする基礎控除のほかに、住民税の計算をする基礎控除もあります。
住民税の基礎控除は43万円になります。
年収103万円の給与収入の場合、
【所得税】給与収入103万-給与所得控除額55万ー基礎控除48万=給与所得金額0円
【住民税】給与収入103万-給与所得控除額55万ー基礎控除43万=給与所得金額5万円
年収103万円の人は、所得税はかかりませんが住民税については課税されるということになります。
給与所得5万円になり、住民税課税対象者になります。収入98万円以上が住民税課税ラインです。
つまり、給与収入98万円であれば、所得税と住民税が非課税になります。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は一律ではなく、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式です。
シンプルな計算式なので、法定相続人の数を把握すれば基礎控除額を簡単に求めることができます。
法定相続人とは、民法に基づく相続人を意味し家族構成に応じて自動的に決まります。
死亡者数に占める相続税の課税件数の割合は、平成29年で8.3%になります。
相続税は、ほとんどの日本人には課税されていないということになります。
またの機会に、詳細記事を書こうかと思いますが…90%の日本人には必要のない情報になります。
給与収入と給与所得の違い
年収400万円などというのは、会社員の場合、会社から支給された金額が400万円ということです。
これが、給与収入になります。
所得は、収入から経費を引いた額になります。
個人事業主であれば、売上が収入でそこから売上のために使った経費を引いた金額が所得になります。
これが、事業所得になります。
会社員の場合は、経費ではなく給与所得控除55万円を引いた金額が所得です。
これが、給与所得になります。
会社員の場合、給与収入ー給与所得控除55万円ー基礎控除48万円ー各種所得控除
これが、課税給与所得になります。
年収103万円以下だと所得税が非課税になる理由
納税者の所得が給与所得だけの場合に、年収が103万円を超えると所得税が課税されます。
年収103万円以下であれば、この課税所得額が0円。
0円に税率を掛けても0円ですから、所得税が課されないことになるわけです。

ここがポイント‼
《給与収入103万-給与所得控除55万ー基礎控除48万=給与所得金額0円(所得課税額0円)》《これが103万円の壁の仕組みになります。理解しておくと便利です。》
基礎控除の控除額
合計所得金額2,400万円以下…所得税48万円・住民税43万円←ほとんどの国民は、こちらです。
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…所得税32万円・住民税29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…所得税16万円・住民税15万円
合計所得金額2,500万円超…所得税0円・住民税0円
基礎控除を受けるには、その年の最後の給与までに、会社へ給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書という書類を会社へ提出します。
まとめ
基礎控除とは、すべての納税者を対象に無条件で差し引く所得控除のことになります。
給与収入103万円であれば、所得税が非課税になります。
給与収入98万円であれば、所得税と住民税が非課税になります。
103万円の壁は、所得税非課税者です。
98万円の壁は、所得税非課税者・住民税非課税者になります。

家族全員が住民税非課税者であれば、ニュースでよく見る住民税非課税世帯になります。
住民税非課税世帯の方は、国の給付金などの援助を受けることができます。
98万円の壁も存在しますので、いろいろな検討の材料に加えていただけると幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
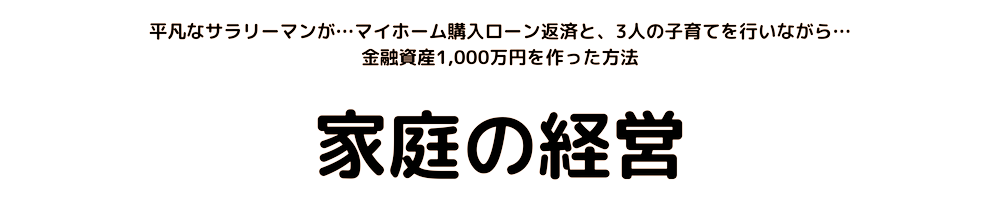
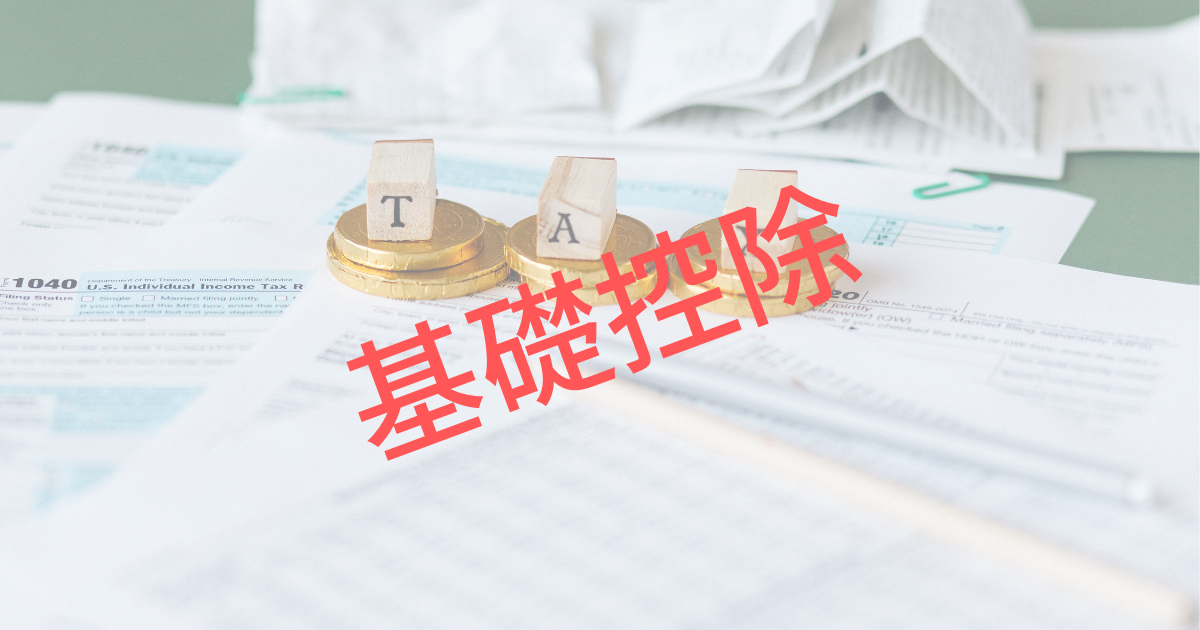
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント