児童手当とは

児童手当とは、子供が生まれてから中学校卒業までの約15年間にわたり給付される手当になります。
お住まいの自治体より給付されるので、ホームページなどで確認することができます。
支給額は、3歳までは15,000円・3歳以上小学校修了前は10,000円・中学生10,000円になります。
支給時期は、6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
4か月分の手当が後払いで支給されます。例えば6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
所得制限限度額(622万円以上)や所得上限限度額(858万円以上)で、減額されることもあります。
支給対象者
①自治体に住所を有し、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している人
②児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
③父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。
④単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
⑤未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
➅外国籍の方は、外国人登録原票に登録されている正規在留者に限ります。(ただし、短期滞在の在留資格者を除く)
⑦公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。
認定請求に必要な添付書類
①健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
②印鑑(省略可)
③請求者名義の通帳
④請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
⑤届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
➅委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
⑦児童が別居している場合…別居監護申立書
⑧請求者の子でない児童を養育している場合…養育申立書
⑨請求者が本年1月1日現在海外に居住していた場合…申立書・パスポート
支給額 所得制限限度額未満の方(児童手当)
3歳未満…月額15,000円
3歳~小学校修了前…月額10,000円(第3子以降は、月額15,000円)
中学生…月額10,000円
支給額 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方(特例給付)
3歳未満…月額一律5,000円
3歳~小学校修了前…月額一律5,000円
中学生…月額一律5,000円
所得制限
⓪扶養親族等の数・0人…所得制限限度額622万円・所得上限限度額858万円
①扶養親族等の数・1人…所得制限限度額660万円・所得上限限度額896万円
②扶養親族等の数・2人…所得制限限度額698万円・所得上限限度額934万円
③扶養親族等の数・3人…所得制限限度額736万円・所得上限限度額972万円
④扶養親族等の数・4人…所得制限限度額774万円・所得上限限度額1,010万円
⑤扶養親族等の数・5人…所得制限限度額812万円・所得上限限度額1,048万円
支給開始月
児童手当の受給者が認定請求をした日(申請日)が属する月の翌月分から支給されます。
①児童の出生日の翌日から起算して15日以内に認定請求
②転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求
③公務員を退職された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求
出生日・転出予定日・退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
支給日
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
支給日は各市町村で異なりますので、入金は振込日以降に通帳等で確認してください。
各種手続きについて
児童手当認定請求書
①児童が出生したとき
②受給者が転入したとき
③受給者が公務員を退職し、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
④その他、新たに児童の養育を開始したとき
額改定認定請求書(増額)
出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき
額改定届(減額)
児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき
受給事由消滅届
①受給者が国外転出し、国内で対象児童を監護する配偶者が受給者となるとき
②受給者が公務員になったとき
③受給者が離婚等により、児童を監護しなくなったときや、生計を同一としなくなったとき
④受給者が逮捕・未決勾留または刑務所に収監されたとき
⑤児童が施設等に入所したとき
児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求が行われます。
別居監護申立書
受給者の子でない児童を養育している方が、児童手当の認定請求をするとき
父母に養育されていない児童を、祖父・祖母、またはその他の方が養育している場合など
未支払請求書
受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき
支払希望金融機関変更届
振込先口座を解約または変更したとき(氏名変更の場合も手続きが必要です)
まとめ
10月から、中学生以下の子どもに支給されている児童手当について、親の所得が上限を超える家庭への支給が廃止されました。親の所得が所得上限限度額を超えると全く支給されなくなりました。
所得は夫婦どちらか高いほうで判定されるため、共働きでも2人の収入が合算されることはありません。
子ども2人と専業主婦がいる会社員の場合、年収1200万円以上は児童手当を受け取れなくなりました。
我が家の場合は、所得制限を受けることなく、3人分受給することができました。

当時は、1人目5,000円・2人目5,000円・3人目以降10,000円であったかと思います。

少子高齢化対策として、当時より増額されています。制度の変更を最大限に活用しましょう。

ここがポイント‼
《児童手当を貯蓄されている方も多いと思います。
児童手当を利用して、子供に経験投資をしましょう!
旅行に行ったり、外食に行ったり、イベント参加したり
我が家は、レジャー費として児童手当を活用していました。》
経験投資をしたことによって、『勘のいい大人』に成長してくれたかなぁと思っています。
子どもがいただいた児童手当です。子どもの経験蓄積に使うのもいいかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
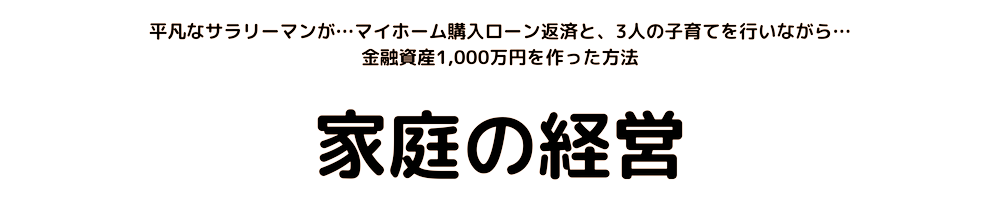

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


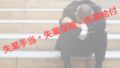
コメント