遺産相続とは
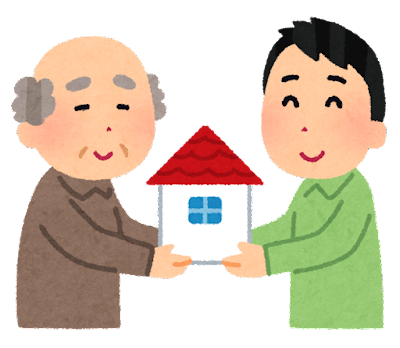
親族などが亡くなって、相続が発生した時に相続人は下記の三つより相続の選択をします。
①単純承認…相続人が亡くなった方(被相続人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ相続。
②限定承認…亡くなった方(被相続人)の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続。
③相続放棄…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続。
相続の場面では、多種多様な選択になるかと思います。詳細不明な場面も多いです。
それぞれの場面に適した相続の選択をしましょう。
相続放棄とは、亡くなった方に負債があった時に、家庭裁判所の申述を行い負債を受け継がないことを裁判所に受理していただき、債務者から自己権利を守る法的な対処法になります。
単純承認
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法になります。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認又は相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
しかし、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められません。
単純承認したことになる一般的なケース
①相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
②相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
③相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。また私的に消費したとき。
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても自動的に単純承認になります。
単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。
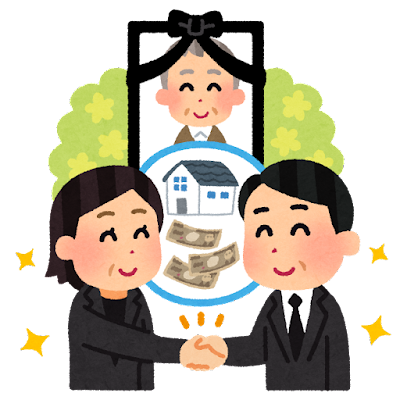
限定承認
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産の範内でマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法のことになります。
限定承認は単純承認にくらべ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあります。
利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
家庭裁判所に限定承認申述をする必要があります。
限定承認が有効なケース
①債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
②債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
③債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
④家業を継いでいく場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
⑤家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
相続が発生した早い段階から相続人や相続財産を調査して、相続しても良いものなのかするべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
限定承認の流れ
①家庭裁判所に限定承認申述をします。
②家庭裁判所から審判書の謄本を交付します。
③相続債権者への債権届出の公告をします。
④配当弁済手続をします。
⑤家庭裁判所への鑑定人選任の申立します。
⑥残余財産の処理をします。
相続放棄
被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることができます。
相続では、不動産や現金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
多大な借金があった場合、相続人その財産や借金の相続を引き継がないと申請することができます。
基本的には、「すべてを相続する」または「すべてを放棄する」しか選べず、「これは相続するけど、これは相続しない」ということはできません。
原則として、3ヶ月以内であれば裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。
民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続人が複数いる場合には、一部の人のみが相続放棄することも可能になりますし、全員が放棄するということも可能です。
相続対象となるもの
プラスの財産…不動産・現金・有価証券・自動車など
マイナスの財産…借金・住宅ローン・損害賠償請求権・損害賠償責任など
相続放棄の進め方

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後に住所地の家庭裁判所に相続放棄の手続きを行います。
レターパックなどの証明郵便を用いて、郵送にての手続きも可能です。
家庭裁判所に相続放棄申述をします
裁判所のホームページより申述書をダウンロードして、記載例を参考に記入します。
申述に必要な書類と費用
①相続放棄申述書(2枚で1組)
②収入印紙800円分(申述人1人につき)
③返信用の郵便切手(例:84円切手3枚・10円切手1枚)申述先の家庭裁判所に確認してください。
④添付証明書(戸籍謄本など)
必要添付書類共通
①被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票
②申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が被相続人の配偶者の場合
③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫・ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
③ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
④申述人が代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合・父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
④ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
⑥申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申述後について
申述書を提出した後、審理のために必要な場合、追加書類の提出、照会書の送付をすることがあります。
受理されたら(認められたら)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
別途申請すれば、相続放棄申述受理証明書(収入印紙150円)を発行していただけます。
まとめ
我が家の場合は、亡き父の兄弟姉妹が多額の負債が判明したため、相続放棄を申述し受理されました。
相続自体は、3件目になります。

1件目…単純承認。
遺産相続協議書を自分で作成して、法定相続人の方に署名捺印いただき、現金を協議相続しました。

2件目…単純承認。
司法書士さんに依頼して、遺産分割協議書を作成していただき、法定相続人の方に捺印いただき
不動産を協議相続しました。

3件目…相続放棄。
自分で家庭裁判所に相続放棄申述をして、相続放棄申述受理通知書・相続放棄申述受証明書をいただき、無事に相続放棄できました。

相続は、そんなに難しくありません。
自分でもできますし、司法書士さんにお願いして行うこともできます。
限定承認・相続放棄でお困りの方は、家庭裁判所で教えていただくことをおすすめします。
優しく教えていただけます。

おまけ:相続税を支払うのは、日本の人口の約8%ほどです。
日本国民の92%の方々には関係ないお話です。
相続対策は必要かと思いますが、
相続税対策はほとんどのかたは必要ありません。

相続タイミングは突然やってきます。
家族の資産・負債を日常的に情報交換しておくのも、おすすめです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
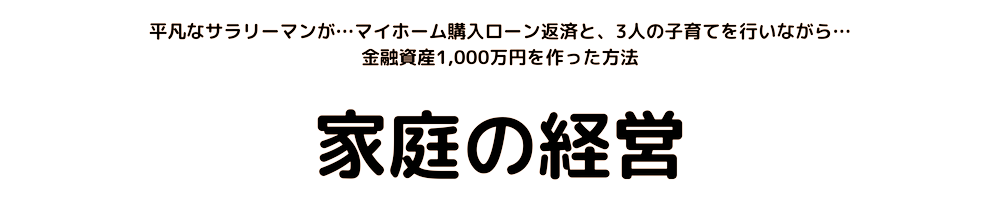

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント