固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課税されます。
住宅や田んぼなどの土地、住宅やお店などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産を総称して固定資産と呼びます。
償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことをいいます。
固定資産の所有者がその資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めます。
都市計画税とは、市街化区域内に土地と建物を所有している人のみが納税の対象となります。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税です。
4月~6月頃に市町村から届く納税通知書に従って、固定資産税と併せて納税することになっています。
固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)になります。
徴収した市町村により、道路や学校・公園など日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスにも使われています。
固定資産税
課税対象資産…固定資産(土地・家屋・償却資産)
納税義務者…1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有する人
課税標準…固定資産税評価額
税率…1.4%
都市計画税
課税対象資産…市街化区域内の土地・家屋
納税義務者…1月1日現在、市街化区域内の土地・家屋を所有する人
課税標準…固定資産税評価額
税率…0.3%(制限税率)
固定資産税の計算方法
固定資産税の税額=固定資産の評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
固定資産の評価額(課税標準額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづき各市町村の長が一つ一つの固定資産を評価し算出したものです。
固定資産の評価額は、土地や家屋の時価によって変動するため、土地や家屋の評価は3年に一度見直されています。
評価替えのタイミングで、土地の時価が上がっていれば、固定資産の評価額(課税標準額)が上がり、その年から固定資産税の税額も上がるということになります。
固定資産税の税負担を軽減する特例措置
固定資産税には減額や減免などの措置があり、税負担が軽減されることがあります。
新築住宅を購入する人なら新築住宅の減額特例措置、すでに住宅を持っている人ならば耐震改修やバリアフリー改修に関する特例措置を受けることができます。
新築住宅の減額特例
2024年3月31日までに新築された住宅には、減額特例が適用されます。
この減額特例では、課税される床面積120㎡までの部分の税額が2分の1に軽減されます。
一般住宅
一般の住宅…3年度分の減額期間
3階建以上で準耐火・耐火構造を有する住宅…5年度分の減額期間
長期優良住宅
一般の長期優良住宅…5年度分の減額期間
3階建以上で準耐火・耐火構造を有する長期優良住宅…7年度分の減額期間
土地の減額特例
マイホームの土地(住宅用地)については、200㎡までの部分の課税標準を6分の1で計算する特例があります。(200㎡超で床面積の10倍までの部分は3分の1)
固定資産税の納付に関する注意点
①滞納すると延滞金が発生する…固定資産税は納付期限が決められており、滞納した場合は延滞金が加算されます。納付期限の翌日から1カ月を過ぎると延滞金の税率が上がります。
②固定資産税の減額・減免措置には申告が必要…特例措置を受けるには申告が必要です。固定資産税の減額・減免措置の内容や申告方法については、課税地の市町村に確認します。
まとめ
我が家の場合は、既存の住宅を解体し23年前に新築住宅を建てました。築23年目です。
現在の固定資産税額は土地・建物で52,000円ほどになりますが、当時は10万円を超えていました。
新築住宅は課税標準額が高いので、減額特例があってもかなり高額でした。
築年数が進むと減価償却していくので、建物の課税標準額が下がっていきます。
5年の新築住宅減額特例があると、建物の減価償却も進みます。
23年目にもなると、当時の課税標準額の1/10ほどになっています。
もちろん売るときも1/10なので、単純に価値が下がったことになります。

毎年恒例になっていますが、4月に固定資産税・5月に自動車税の納付があります。

固定資産税・都市計画税税を支払うのには、税金対応積立が必要になります。

ここがポイント‼
《固定資産税想定納付額と自動車税想定納付額を足して12で割った金額を毎月積み立てていきましょう!そうすることで、4月・5月の高額納税期間に容易に対応することができます。》

賃貸アパートマンションにお住いの方、車を所有してない方は全く納付する必要はありません。

その分、金融投資・経験投資・自己投資に回してください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
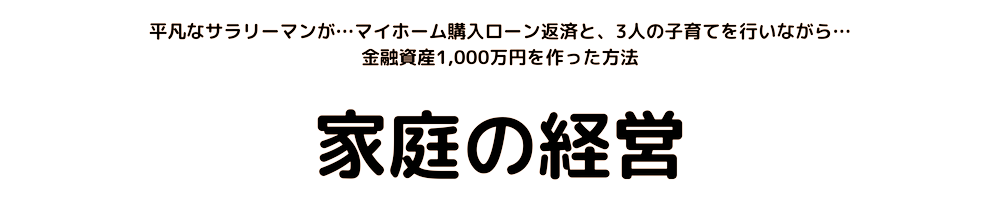

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント