ディマンド・リスポンス(DR)とは

ディマンド・リスポンス(DR)とは、消費者が賢く電力使用量を制御することで電力需要パターンを変化させることです。
これにより、電力の需要と供給のバランスをとることができます。
私たちの生活に欠かせない電気を安定して供給するためには、電気をつくる量(供給)と電気の消費量(需要)が同じ時に同じ量になっている必要があります。
これらの量が常に一致していないと、電気の品質が乱れてしまい電気の供給を正常に行うことができなくなってしまいます。
電気は貯めることができないため、その日その時に使う電気は毎日生産し必要になった都度供給しなければなりません。
需要が多い時期には電力需給がひっ迫する一方、需要が少ない時期には供給が過剰になり、再エネの電気が余ることもあります。
こうした状況を背景として、エネルギーの需要側が供給状況に応じて賢く消費パターンを変化させるDRの重要性が高まっているのです。
ディマンド・リスポンス(DR)の種類
ディマインド・リスポンス(DR)は、需要制御のパターンによって、需要を減らす(抑制する)「下げDR」と、需要を増やす(創出する)「上げDR」の二つに区分されます。
上げDR
DRの発動状況により電気の供給量を増やします。
再生可能エネルギーの過剰出力分を需要機器を稼働して消費したり、蓄電池を充電することにより吸収したりします。
下げDR
DRの発動により電気の需要を減らします。
電気のピーク需要のタイミングで需要機器の出力を落とし、需要と供給のバランスを取ります。
上げ下げDR
上げDRと下げDRにより、電気の需要量を増やしたり減らしたりすることを上げ下げDRといいます。
送電線に流れる電気の量を微調整することで、電気の品質を一定に保ちます。
需要制御の方法
①電気料金型ディマンド・リスポンス
②インセンティブ型ディマンド・リスポンス
電気料金型ディマンド・リスポンス
ピーク時に電気料金を上げることで、各家庭や事業所に電力需要の抑制を促す仕組みのこと。
比較的簡便であり大多数に適用できるというメリットもあるが、時々の需要反応によるため効果が不確実であるというデメリットがある。
インセンティブ型ディマンド・リスポンス
電力会社との間であらかじめピーク時の節電による契約を結んだ上で、電力会社からの依頼に応じて節電した場合に対価を得る仕組みのこと。
契約によるため効果が確実であるというメリットもあるが、比較的手間がかかり小口需要への適用が困難であるというデメリットがある。
ディマンド・リスポンス(DR)の手法
ディマンド・リスポンスにより、電力需要をコントロールする。
①調整・停止(空調・照明など)
空調や照明などの負担設備を調整・停止させることで電力需要を抑制します。
②生産計画の変更
生産設備を調整・停止させることで電力需要を抑制します。
変更させた分は夜間などにシフトすることで生産量を維持します。
③放電(蓄電池など)
下げDR依頼の時間帯に蓄電池から放電した電気を使うことによって、その時間帯における電力会社からの電力供給を抑制します。
④充電(蓄電池など)
上げDR依頼の時間帯に蓄電池を充電することで、その時間帯の電力需要を創出します。
まとめ
ディマンド・リスポンス(DR)は、全体の電力需給バランスの改善するだけでなく、電力使用量を抑えることで、高騰するLNG(液化天然ガス)などの燃料原料の購入量を減らすことができます。
日本全体として、発電のための燃料調達コストを抑制できるというメリットがあります。
再エネの導入拡大によって電力供給が過剰となっているタイミングでは、ディマンド・リスポンス(DR)により需要時間帯をシフトすることで再エネの電力を有効に使うこともできます。
家庭や企業側から考えると、電気料金の負担抑制や(電気料金型DR)電力会社からの報酬が得られる(インセンティブ型DR)というメリットがあります。

ここがポイント‼
《電気を賢く効率的に使用するディマンド・リスポンス(DR)は、日本全体にとっても、個人にとっても、メリットを得られる国の取り組みであると思います。》

我が家も、太陽光発電システムと蓄電池システムを導入してディマンド・リスポンス(DR)の取り組みを微力ながら行っています。
節電も大切かと思いますが、賢く効率的に電気を使用することも大切かと思います。
国の取り組み方針を理解し、上手に暮らしていけたらと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
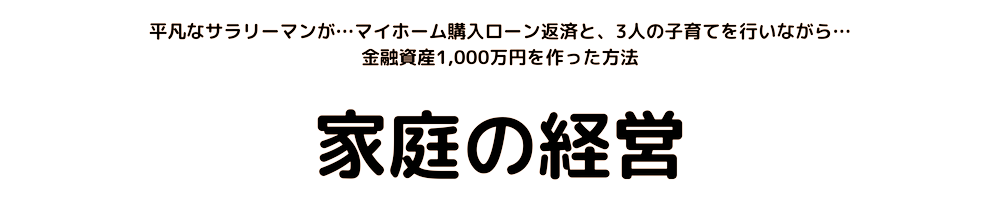
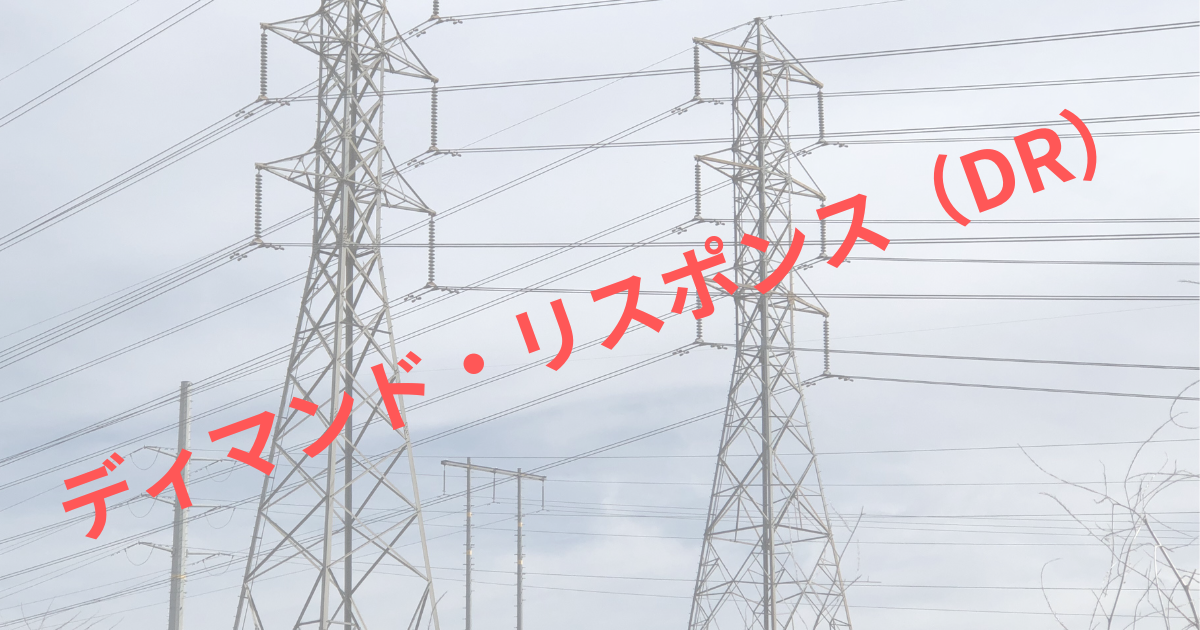
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント