燃料調整額とは

最近、電気代が高くなったなぁ~と感じる方も多いかと思います。
輸入燃料原料の高騰や人件費の高騰などのインフレ要因が考えられます。
特に、冬の電力は暖房などで消費量が多くなりますので、影響も大きいと思います。
我が家もオール電化住宅のため、最大級の影響を受けているのが現状です。
電気代高騰のご家庭と電気代+ガス代+灯油代高騰のご家庭は同じことになります。
電気料金の内訳にある燃料調整額についてのご存じでしょうか?
燃料費調整額とは、毎月の電気代に含まれる費用の一つで、燃料費調整制度に基づいて設定される燃料費調整単価に使用電力量をかけて計算されて電気料金として請求されています。
輸入する燃料費の価格の変動に応じて、加算あるいは差引きで計算されます。
燃料費調整制度とは
燃料調整制度とは、火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動を電気料金に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。
日本の電力構成は、火力発電が約76%・再生可能エネルギーが約10%・水力約8%、原子力約6%となっており、7割以上の発電を火力発電に依存しています。
火力発電の内訳は、液化天然ガス約37%・石炭約32%、石油等約7%です。
日本のエネルギーの3/4は火力発電になります。
使用する化石燃料(原油、LNG、石炭)のほとんどは海外からの輸入に頼っており、輸入先の国々の経済状況や政局などの情勢によって価格が変動します。
燃料価格が高騰したときに発電事業者が大きな損失を受ける可能性があります。
事業者を守るため、1996年に燃料費調整制度が設けられました。
制度設立当初は燃料費の変動が反映されるのは年4回だけでしたが、2009年の制度改正から2ヶ月後に燃料費の価格変動がより迅速に電気料金へ反映されるようになりました。
燃料費調整制度のプラス・マイナス調整
燃料費調整制度では、燃料価格の変動に連動した燃料費調整額が電気料金に反映されます。
平均燃料価格を基準燃料価格として、基準燃料価格より高ければ燃料調整単価にプラス調整がされ、低ければマイナス調整がされます。
燃料費調整制度のプラス調整
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 – 基準燃料価格) × 基準単価 ÷ 1,000
燃料費調整制度のマイナス調整
燃料費調整単価 = (基準燃料価格 – 平均燃料価格) × 基準単価 ÷ 1,000
燃料費調整額の算定方法
燃料費調整額は、燃料費調整単価にその月の電力使用量をかけることで求めることができます。
燃料費調整額(円)=燃料費調整単価(円)×1カ月の電力使用量(kWh)
燃料費調整単価はkWhあたりの金額で算出されるので、電力使用量が多ければ燃料費調整額も比例して大きくなります。
基準燃料価格とは
基準燃料価格は、電力会社が料金プランを作った当時に想定していた平均燃料価格のことで、この価格を前提に燃料費調整単価が求められます。
平均燃料価格の求め方
平均燃料価格は、原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計価格を原油と同じ熱量・数量単位に換算し、平均燃料価格を算定します。
むずかしいので参考までに…
平均燃料価格=平均原油価格×α+平均LNG価格×β+平均石炭価格×γ
燃料費調整単価の算定方法
平均燃料価格を95,000円・基準価格を44,000円・基準単価を22.5銭とします。
上回るためプラス調整の下記の式に当てはめて燃料費調整単価を求めます。
燃料費調整単価(銭/kWh) :(平均燃料価格 – 基準燃料価格) × 基準単価 ÷ 1,000
燃料費調整単価(銭/kWh) :(95,000– 44,000)×22.5÷1000=1147.5(銭)→11.47円
反映タイミング
燃料調整単価は、3ヶ月間の貿易統計価格に基づき算定された2ヶ月後に反映されます。
1月分から3月分の燃料価格の平均燃料価格は6月分の電気料金に反映されます。
燃料費調整単価の推移
燃料費調整単価が一番安い2021年1月から2022年9月を比較すると、1kWhあたり約11.5円の値上がりとなっています。
燃料費調整額高騰の主な要因として挙げられるのは燃料価格の高騰です。
日本のエネルギーは、約7割が火力発電でその燃料は海外から輸入しています。
そのため、原材料の高騰は燃料費調整額にも大きな影響が出ます。
燃料費調整額の高騰は今後も続いていくことが十分想定することができます。
エネルギー価格高騰の要因
原材料のエネルギー価格の高騰にはさまざまな要因があります。
①新型コロナウイルスの影響
②脱炭素社会実現の影響
③ロシア軍のウクライナ侵攻と世界情勢の影響
④円安の影響
まとめ
我が家はオール電化住宅で太陽光発電+蓄電池システムを設置していますが、電気代高騰の影響を受けています。
電気料金明細は、基本料金(定額)と電力量料金(従量)の2本立てになっています。
燃料調整額は、電力量料金に含まれています。
2023年1月の燃料調整単価は、12円30銭/kWhになっています。
2022年1月の燃料調整単価は、-0円44銭/kWhでした。12円74銭/kWhの値上がりになります。

契約プラン平均電力量料金は約25円なので、約50%の値上がりです。
2022年1月の電気使用量は、1,950kWhでした。年間で最大電気使用量の月になります。
燃料調整額は、2022年1月は-858円で2023年1月は+23,985円になります。

単純に25,000円ほどの値上がりになります。直撃ですね。
電気使用量が多い理由は夜間就寝時間中エアコン運転と外気温が低く日照時間が短いことと思います。
エアコン冷房運転は、設定温度になると電気料金はほとんどかかりません。
エアコン暖房運転は、設定温度のなっても電気料金が加算方式で積みあがっていきます。
冬のエアコン電気代が高額になるのは当然の結果です。

就寝中に気温の変化が大きいと、無防備な身体が影響を受けます。
電気代を節約しても、医療費が増えてしまっては本末転倒です。
電気代は必要になりますが、安眠が日中活動の原動力になります。
人的資本が重要です。我が家は生活環境に投資しています。
あくまでも我が家の考え方です。
ご参考までに。

燃料調整額は、避けることのできないコストです。上手にお付き合いしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
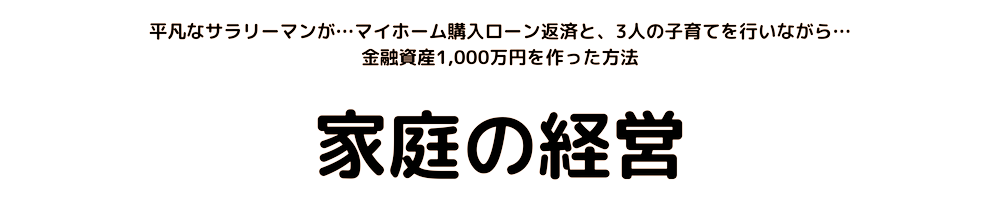

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


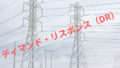
コメント